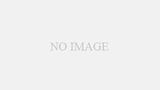トランプ大統領の誕生、イギリスのEU離脱など、先を読むことが難しい現代ですが、そんな中でも日本人は世界屈指の長寿を誇り、老後の安心は誰もが願うところです。
一方で、長引く低金利で、公的年金だけで豊かな老後を送ることは期待薄です。
かつてのような右肩上がりの経済成長で、預貯金の金利が5%もあれば、1000万円の貯蓄があれば、毎年50万円の利息収入を見込むことができて、利息の分だけ使って元本を維持していれば、毎年同じ収入がありましたが、現在の金利水準で、毎年50万円使えば、1000万円の貯蓄は20年でなくなってしまいます。
人は誰でもいつかは亡くなるので、寿命がわかっていれば、お金が枯渇しないようにちょうどよく使うこともできますが、実際には、いつまで生きられるかわからないので、慎重に節約しながら生活をしています。
働きながら給料を稼ぐなどの収入の手段=生活の糧があれば心配はいりませんが、多くの人は、働くことで収入を得られるのは70歳くらいまでです。
そのあとの老後も、貯蓄を取り崩す心配なく生活するには、働かなくても得ることができる”不労所得”が必要です。
不労所得の代表格が不動産投資、賃貸経営です。
不動産投資、賃貸経営といえば、多額の初期投資が必要で、敷居が高いものと考えがちですが、そのハードルを越える方法は二つあります。
一つは、不動産の資産価値を担保に借入をして、家賃収入を返済に充てることで、少ない手元資金でも始めることができる方法です。
借入返済の間は収入は手元に残りませんが、手元資金の持ち出しを最小限にして、将来、返済が終わった後には名実ともに自分の財産となり、現在の低金利もこの方法を後押ししています。
この方法の弱点は、空室で収入がなくても、返済は待ってくれないので、空室リスクの回避がポイントになります。
もう一つの方法が、みんなで大家さんのように、投資物件を小口に分散して、複数の投資家がその収益を分配する、信託投資の方法です。
投資一口の金額が、不動産への直接投資よりも小さいので、借り入れのリスクを取らずに、手元資金で可能な範囲の投資ができること、賃借人の募集や物件の管理など、賃貸経営をプロに任して、収益の分配だけを受けられることが魅力です。
また、例えば投資資金が2000万円あるとして、2000万円の投資物件を一つ持っていると、空室になった場合の収入は0になってしまいますが、100万円の投資を20件の投資物件に分散投資していれば、収入が0になるリスクは格段に小さくなります。
誤解されがちなことですが、不動産を所有して、賃貸経営は、危険なものではありませんが、何もしなくてもお金が入ってくるものでもありません。
労働する必要がないという意味では”不労”所得で、高齢になっても続けることができますが、入居者の募集、物件の維持管理など不動産管理業務が必要です。
持っているだけで、空き家になってしまえば、固定資産税や設備の維持費などの費用が掛かるばかりなので、家賃を下げても入居者を見つけたほうが有利な場合もある反面、一度引き下げた家賃は、入居者が変わった後も引き上げるのは至難の業です。
住宅設備を豪華にして入居者への魅力をアップするか、設備を豪華にする代わりに、手ごろな家賃で価格競争力をつけるかも経営判断です。
みんなで大家さんなら、物件の管理や入居者募集などの賃貸経営は、専任のプロフェッショナルに任せることができるので、オーナーは経営の心配なく、収益だけを受けとることができます。
不動産を投資対象とする投資信託には、REIT(Real Estate Investment Trust)があり、みんなで大家さんも、広い意味では不動産投資信託の一つですが、一般に証券会社などで販売されているREITは、より多くの資金を集め、投資対象を賃貸住宅や商業物件などのくくりで幅広く選択していることから、投資対象の物件ごとの経営成績が見えにくく、不動産に対する投資をしているというよりも、金融商品の性格がより色濃くなっています。
みんなで大家さんは、保有する口ごとに投資対象の物件がわかっているので、物件ごとの経営成績の透明性が高く、不動産投資をしている実感、確かな利回りが目に見えるのが、一般的な投資手法のREITと比較した場合のメリットです。
不動産投資初心者にとっては、借り入れによる資金調達リスクを避けること、賃貸経営に専門家の手腕を借りられることが魅力ですが、経験者や上級者にとっては、分散投資による空室リスクの回避が魅力になります。
初心者から上級者に至るまで、幅広い層にとって、それぞれの魅力を活かして不動産に投資できるのが、みんなで大家さんです。
そのため、投資口数の追加購入のようなリピーターも多いのがこの商品の特徴です。
その場合、投資対象の物件は、同じものには投資せず、他の物件に投資するので分散投資につながります。