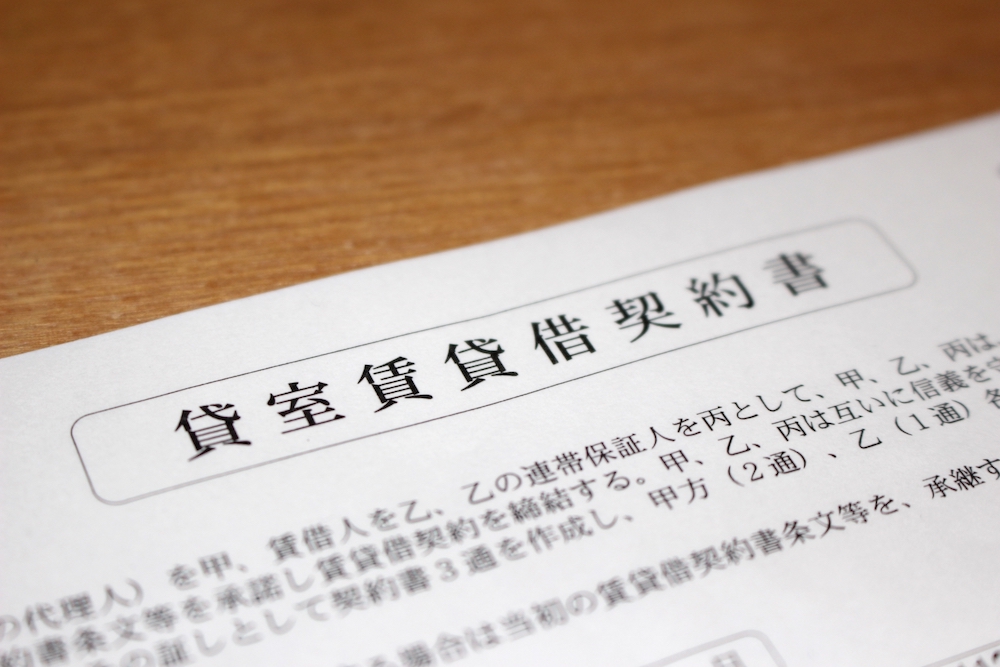我が国の税制には控除とよばれるしくみがありますが、これは所得控除と税額控除といった異なるタイプにわかれています。
所得控除は課税対象となっている所得金額から一定の金額を差し引くことであり、税額控除は税金そのものから一定の金額を差し引くことです。
所得税のしくみ上、会社で働いて得られた給料その他の収入のすべてが課税対象となることはなく、そこから収入を得るためにかかった費用をいったん差し引いた金額にあたる所得に対して、法律で定められた一定の税額を掛け算して税額を求めます。
その際に所得控除があったとすれば、税率で掛け算をする前の所得の金額が安くなるので、必然的に税額のほうも軽くなります。
さらに税額控除の場合は掛け算をしたあとの税額からの差し引きとなりますので、やはり実際に納税すべき税額が安くなる点では同様です。
ただし計算をしてみるとどちらのほうが納税者にとってメリットがあるか、すなわち実際の納税額がより少なくなるかは異なりますので、法律でどちらでも認められている場合にはメリットの多いほうを選択することになります。
控除の種類
控除にはいろいろな種類があり、世間でよく聞かれるのは社会保険料控除ですが、これは国民年金保険料や国民健康保険料といった社会保障関連の料金を支払った場合に、その全額を所得のなかから差し引くことができるしくみです。
医療費控除は健康保険が適用される病院での診察や入院・通院にかかった費用その他医薬品代などの自己負担額が原則として年間10万円を超えた場合に、その超えた部分の金額が所得から控除されるしくみとなっており、国民の医療費の負担を軽減する効果があります。
個人が住宅ローンを利用してマイホームの新築や増改築を行った場合について、ローンの残債をもとに毎年の所得税額から一定額を差し引くことができる住宅借入金等特別控除などもあります。
寄附金控除について
このようなしくみが控除とよばれるものですが、なかでも寄附金控除は納税者が日本ユニセフ協会などの団体などに寄附をした際に適用されるものであり、公共の福祉などにたずさわっている団体への寄附を税制上もうながすために設けられた制度です。
したがって単に寄附の相手方が団体であればよいというのではなく、法令によって適用対象となる条件がこまかく決められています。
法令用語としては特定寄附金となっていますので、この用語にあてはまるお金がまずは対象となります。
具体的には国や地方公共団体に対する寄附金や、広く一般に募集されていて緊急性があるものとして財務大臣が指定したものなどがあります。
ほかには独立行政法人や社会福祉法人、公益社団法人・公益財団法人、私立学校法の学校法人などの主たる業務に関連した寄附も該当します。
さらには認定NPO法人や政治団体などに対するものも同様となっています。
寄附金控除の金額
寄附金控除の金額についても法令で決まっていますが、その年に支出した特定寄附金の合計額と、その年の総所得金額等の40パーセントに相当する額とを比較して、どちらか低いほうの金額から2千円を差し引いた金額とされています。
また寄附金控除は基本的には所得控除のタイプに該当していますが、政治活動に関するもの、認定NPO法人に対するもの、一定の公益社団法人等に対するものについては、所得控除のかわりに税額控除を選ぶことができます。
計算をしてみるとわかりますが、高額所得者がこの制度の適用を受ける場合、もしもどちらかのタイプを選べるのであれば、税額控除のほうを選択したほうが、結果として納税しなければならない税額が大幅に安くなることがありますので、あらかじめよく調べておくことがたいせつです。
寄附金控除を受けるために
寄附金控除を受けるためには一定の手続きが必要であり、何もしなければせっかくの制度の適用はないものと考えたほうがよいでしょう。
会社に勤務しているサラリーマンの場合には、会社が所得税を給料から天引きしているのでなじみが薄いはずですが、もしもこの制度の適用を受けようと思えば、期日までに税務署に対して確定申告をすることが必要です。
確定申告のための申告書には寄附金控除の欄が設けられていますので、ここに実際に寄附した金額や相手先などの必要事項を記載した上で税務署の窓口に提出をしますが、その際には添付書類としていくつかの証拠も求められます。
基本的には相手方の団体や法人から交付を受けた受領証・領収書ですが、そのほかに特定公益増進法人などといった法令上に該当する法人や団体であることの証明書の写しが求められることがあります。
まとめ
また政治活動関連であれば、選挙管理委員会の確認印がある寄附金控除のための書類をあわせて添付することになっています。
確定申告は原則的に毎年末までの所得について、翌年の2月16日から3月15日までの期間中に管轄する税務署において行うことになっていますが、年によっては土曜日・日曜日や祝日の関係から日付が前後することもあります。