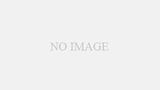画像引用元:保健科学研究所
病院へ行って医師から血液検査を勧められた人も多いかと思います。
血液検査をしてもそれだけですべての病気について特定するのは無理であると思ってください。
一つの病気について採血していくつかの検査をすることはできますが、病気が特定できない場合には複数の検体検査のために何本も採血されることがあります。
そして採血した血液ごとに検査項目を決めて検体検査をするために検査結果が出るまでには時間がかかります。
医師から診察を受けた後に採血をしていくように言われた場合には検査に時間がかかることが多いと考えてください。
医師が想定した範囲内では検査項目が決まっているので比較的1本の採血で済むことが多いですが、いくつかの原因が想定される場合には複数の採血を行って、それぞれについて違う項目の検査を同時に行って可能性を探っていきます。

中には病気の原因が特定されないこともあり、大学病院や専門の研究機関へ検体検査を依頼することもあります。
症例がほとんどない場合には免疫異常が関係していることもあります。
ほとんどの人だけでなく医師までもあまり聞いたことのない病気の一つに日本ではSPSという希少難病があります。
参考→SPS(スティッフパーソン症候群)
これはどんな検査をしても異常がみられることが少なく世界でも症例が少なくて原因も治療法も解明されていません。
100万人に一人が発症するともいわれており、日本では数十人しか確認されていません。
病気が特定されてもGAD抗体が陽性の人もいれば陰性の人もいます。
検体検査も数年前とは異なり血液を希釈するので濃度が低くなりさらに抗体物質の検出が難しくなっています。
現在は血液検査でがんを見つけることも可能になってきています。
しかし、血液検査は万能ではありませんので患者の症状などからも病気の可能性を探っていかなければならないので医師も大変な苦労をすることになります。
検体検査は血液だけに限られたものではありません。
身近なところでは花粉症の検査でも鼻の粘膜などから検体を採取して抗体が検出されるかどうかを確認して対処方法を判断します。
がんなどの検査に有効なのはPETCTを使って全身のがんを探すことです。
口の中の粘膜を採取して悪性の物質を見つけることもできますし、胃がんの検査や大腸がんの検査で異常が見つかった時にも胃カメラなどを挿入して患部から直接検体の採取を行って検査を行います。
意外と身近なところで検体検査のための粘膜などの採取が行われていることは知られていません。
検査で結果が分かるものは治療方法も確立されているので外科手術や内服薬で治癒していくことが期待できます。
しかしながら、原因不明の病気ではどのような検査を行っても特に異常はありません。
先ほどのSPSという病気では症例が少ないこともあって治療をしてくれる医師が少ないのが現状です。
進行性の病気で症状が日を追って変わっていくため何をしたらいいのか分からないからです。
この病気は自分の意思とは関係なく体が痙攣、不随意運動を起こしてしまうのが特徴で、最後には自分の意思で呼吸をすることもできなくなってしまいます。

今のところ回復する見込みがない病気で医療先進国のアメリカで200万円もかけて治療した人もわずか1か月半くらいで元に戻ってしまいました。
日本は医療の開発費が必要なところに分配されていないのでなかなか研究が進んでいないのが現状です。
しかし、それでも他の病気についてはかなり研究が進んでおり、今まであきらめていた病気が治って元気に暮らしている人も大勢います。
少ない症例の病気にはなかなかスポットが当たらないのが日本の医療です。
少しでも希少難病であるSPSという病気の存在に目を向けてほしいのが本当の願いです。希少難病にもかかわらず、なかなか難病指定もされずあまり議題に上がることもないと聞いています。
それでもまだまだ解明されていない病気が少しずつ知られてきたことには期待を持っています。
日本の医療技術も素晴らしいものがあり、いつかは原因も分かって治療法も何か見つかることを祈る気持ちでいっぱいです。
この希少難病が他にもあることに気づかれないで、特に何ともないので様子を見ましょうと医師から言われた患者は見捨てられた気持ちになってしまいます。
医師は患者に希望を与える存在であって決して絶望を与える存在にはなってほしくありません。
いつか時間が経って見つけることができることは多くあると思います。
医師の研究のための時間が無いことは理解できますが、医師にすがるしかない人も大勢いることを分かってほしいと思います。
もう時間が無い人もいる中で優先順位を付けて患者の治療を行って元気で送り出すことに医師は大きな喜びを感じてほしいと思います。
お互いに気を使うことなく経過を正直に話して医師の判断を仰ぐことも必要です。
そして、それに応えるようにするのが医師の大事な使命であることを考えてくれる医師が増えてくれることを願っています。