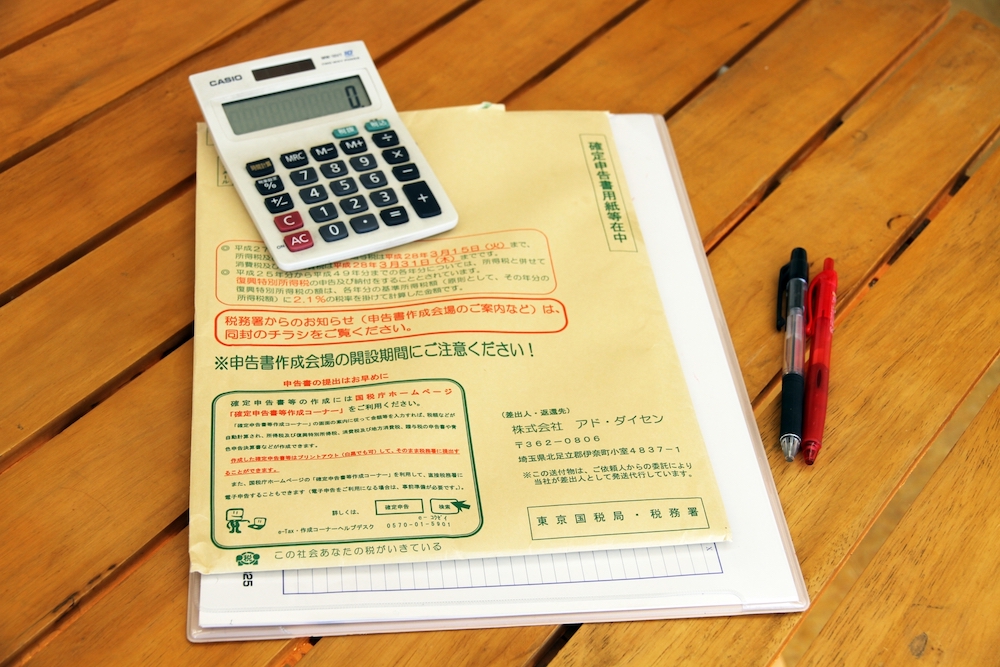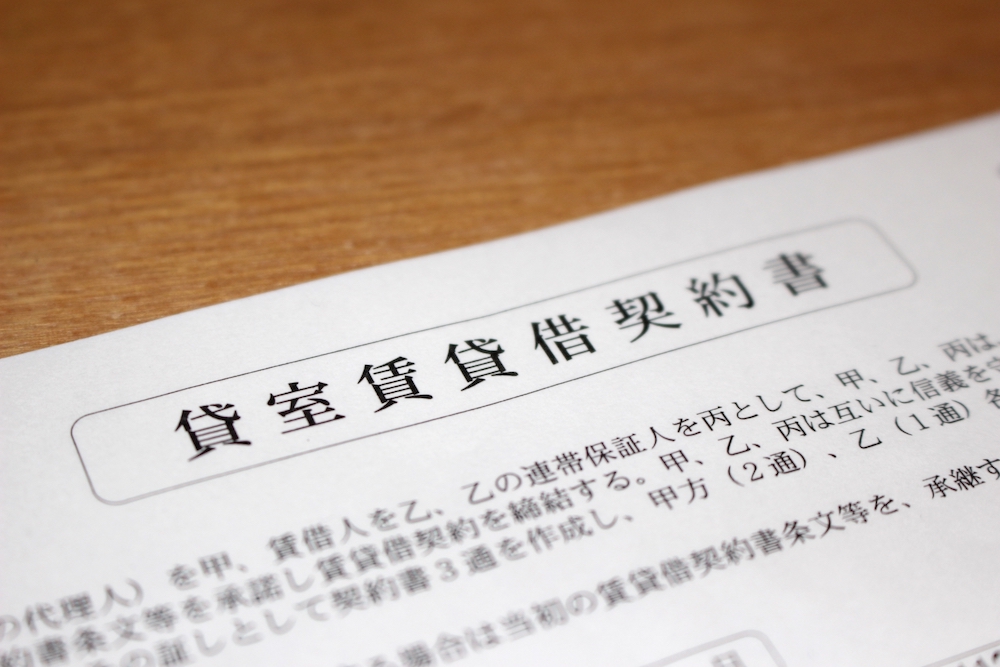税理士になっても資格維持費がそれなりにかかり、まず試験に合格した人が登録し税務に関した業務をするには税理士会への登録が必須です。
登録には必要書類以外に登録免許税が6万円、別に手数料5万円を納付します。
また、入会には会費もかかり毎年大体10万円〜15万円かかると言われていて、この会費は自分が所属するブロック単位の大きな会の会費、支部単位の小さい会の会費に分かれてます。
どちらも金額は会で違い正確な金額は開業したいエリアの会へ問い合わせしないとわかりません。
会に所属する費用について
ブロック単位の大きい会だと、例えば入会金4万円・会館建設費2万円・年会費7万5千円かかり、支部単位の会だとある支部は3万6千円や、他だと6万円など違います。
業務をするときは会への所属が欠かせませんが費用はかかってもメリットは勿論あるようです。
税理士は、納税義務者の信頼にこたえて納税義務の適正な実現が仕事ですが、税務に関した法律や指針は毎年改正されていて、新しい知識が常に必要となってきます。
知識を更新するのに最も良いのが会の各種研修制度で、税務に関した色々な講義を受講出来て受講料も無料から数千円程度と比較的安く、講義に参加することで正しい知識で顧客の期待にも応えられます。
会社員として働いていて登録をするなら、肩書も得られるためクライアントの対応が変わってきたり、難易度の高い仕事にも挑戦出来ますし、別の会社へ転職するときも、登録していることが評価されます。
業務に就かないときは会への登録は不要
業務に就かないときは会への登録は不要で、資格合格者としての地位は守られるので開業するときには登録免許税・手数料・会費を支払うことで肩書は得られます。
独立開業をすると開業費用も必要で、税務会計ソフト購入費・ホームページや名刺作成など営業ツール費・事務所関連費用、プリンタやFAXなどの事務機器やデスクや来客用の応接テーブル費などです。
ホームページなどは自作も可能ですが、業者へ依頼すると約20万円前後はかかり、自宅で開業しないときには事務所としてオフィスなどを借りるので敷金・礼金などの見積もり以外に、設備も最低限揃えないといけません。
近年ではコピー機や無線LANなどの共有可能なレンタルオフィスなどもあり、コスト削減も可能でこれだと敷金や礼金など高額な初期費用も削減可能です。
独立開業するときに負担になるのが家賃で、毎月事務所の賃料が必要で居住専用のマンション等と比べて事務所と使えるスペースだと賃料も高くなります。
家賃相場は地域により違いますが、都内だと数十万円程度はかかりますがレンタルオフィスなら月5万円程度でも借りられます。
大まかな資格維持費
資格維持費は大まかに見ても登録費だけで11万円・入会費が3~5万円程度・年会費が約10~15万円、さらに開業準備費として最低でも100万円ほど必要で、その後の維持費も事務所を借りると約15~25万円、レンタルオフィスなら約5~10万円で他にも通信費や交通費などもかかってきます。
自宅または事務所を借りるかでも費用がかなり異なり、資格を取ってもすぐに独立しないで事務所やファームで実務経験を積んでから給与をもらいながら活躍して、それから勤務先でデスクを間借りし独立準備を経てから独立する人が多いです。
報酬についてはいくつか種類があって契約内容で支払額も変わり、料金設定の明確な基準はないですがある程度の相場は把握できます。
報酬には主に顧問料・作業料金・オプション費用があり、顧問料は顧問契約を交わすと発生し定期的な顧問やそのときに行う各種の指導やアドバイスに対して支払うもので他の業務も含まれたりしますが事務所ごとに違います。
作業料金は、記帳や確定申告の代行を受けるときに費用で、一般的に顧問契約対象外で顧問料とは別に料金設定してます。
同じ業務を依頼されても実際に求められる作業が依頼者により違うこともあって、顧客の要望に柔軟に対応するために各種オプション料金を設定することも出来ます。
各業務での報酬は前は法律で規定されてましが、今は撤廃されて自由に決めることが可能で大体の相場だと、顧問料は月額1~3万円・決算料5~20万円・記帳代行月額1~3万円・確定申告代行5~10万円が多いようです。
顧客を少しでも確保するには料金を安くした方がいいと感じますが、業務での負担を考えないと少ない報酬で多くの作業を処理することになり適正な料金設定でないと依頼が多くても採算がとれなくなります。
まとめ
報酬金額を決める基準には会社の売上高・作業量・難易度があり、依頼内容が同じでもこれらが違うと負担も変わってきます。
会社の売上高が多いほど計算金額も高くなり作業時間も必要で、納税額も増えるので背負う責任も重たくなりますし売上高は決める基準では一般的な要素です。
作業量が多いと負担は大きくなり、料金システムは報酬額が負担に応じて設定される方式が知られていて、年末調整だと作業対象になる従業員が一定の人数を超えると料金が加算されます。
難易度が高いときも料金が追加され、作業日数があまり残ってないときに適用されることが多いようです。